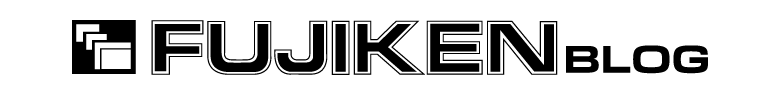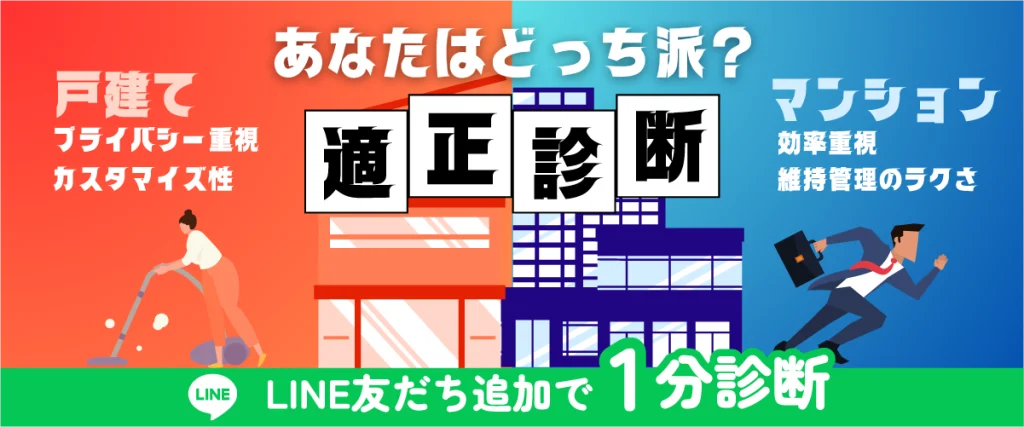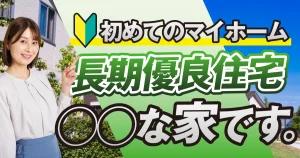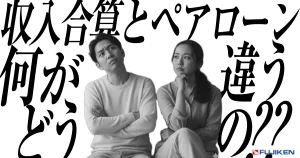近年、核家族化が進む中で注目されているのが「近居」という暮らし方です。親世帯と適度な距離を保ちつつ、必要なときに支え合える近居は、現代の家族のあり方に合った選択肢といえます。しかし、漠然としたイメージだけで近居を選択してしまうと、思わぬ後悔につながるかもしれません。
この記事では、近居の定義やメリット・デメリット、後悔しないためのコツや利用できる補助金制度について詳しく解説します。ご家族にとって最適なライフスタイルを見つけるための参考にしてください。
 フジ犬くん
フジ犬くん近居で暮らしている世帯のデータもご用意いたしました!
近居とは?


近居とは、親世帯と子世帯が別々の住宅に住みながらも、徒歩や自転車などで容易に行き来できる距離に住む状態を指します。具体的には、同じ市内や隣接する市町村、あるいは同じ学区内など、急な用事やちょっとした訪問が気軽にできる範囲をイメージするといいでしょう。
近況はお互いのプライバシーを尊重しつつ、育児のサポートや高齢になった親の介護など、いざという時に助け合いやすい点が最大の魅力です。近年は、共働き家庭の増加や高齢化社会が進んでいます。そのため、家族のつながりを大切にしながらも、それぞれの独立性を保てる近居は、魅力的な選択肢として注目を集めています。
近居以外の暮らし方
二世帯の暮らし方は、近居以外にもいくつかの選択肢があります。主な選択肢としては、同居、隣居、遠居が挙げられます。以下の表に、それぞれの特徴や違いをまとめました。
| 暮らし方 | 定義 | 特徴 |
|---|---|---|
| 同居 | 親世帯と子世帯が同じ一つの住宅で暮らす状態 | ・常に一緒に生活するため、密なコミュニケーションが可能 ・家事や育児、介護の協力がしやすい ・プライバシーの確保が難しい場合がある |
| 隣居 | 親世帯と子世帯が、隣接する敷地や隣り合った集合住宅で暮らす状態 | ・必要に応じてすぐに助け合える ・同居よりはプライバシーを保ちやすい |
| 近居 | 親世帯と子世帯が、徒歩や自転車などで行き来できる距離で暮らす状態 | ・適度な距離感を保ちながら、育児や介護のサポートが可能 ・お互いの独立性を尊重しつつ、いざという時に頼れる安心感がある |
| 道居 | 親世帯と子世帯が物理的に離れた場所に暮らす状態 | ・お互いの生活に干渉することが少なく、それぞれの生活スタイルを確立しやすい ・育児や介護のサポートは難しく、緊急時の対応に時間がかかる |
近居の割合
国土交通省の『住生活総合調査』によると、親と子が近居している割合は約52%でした。近居が過半数を占めているということは、育児世代や高齢化が進む現代における、ニーズの高さがうかがえます。
なお、同居の割合は約23%です。高齢になるほど割合が多くなっています。同居の割合は、子世帯の年齢が上がるにつれて、あるいは親世帯が高齢になるほど高くなる傾向が見られます。
このデータからも、親の健康状態やサポートの必要性、あるいは子世帯の育児支援の観点から、近居が最もバランスが取れた選択肢として選ばれているといえるでしょう。


\ 主要駅から徒歩10分前後の駅近物件ございます! /
近居のメリット
近居は、親世帯と子世帯の双方にとってさまざまなメリットがあります。特に、お互いが一定の距離を保って生活できるため、密な関係を築きつつも、それぞれのプライバシーが尊重される点が大きな魅力です。
近居の主なメリットを、子世帯と親世帯それぞれの視点からまとめました。
| メリット | 子世帯 | 親世帯 |
|---|---|---|
| 育児・教育サポート | 急な送迎や体調不良時に親に頼れる | 孫や子どもと関わり、世代間の絆が深まる |
| 介護のしやすさ | 親の体調急変時にすぐに駆けつけられる | 体調の不安や困り事をすぐに相談できる |
| 健康状態の把握 | 定期的に顔を合わせ、親の異変に気づきやすい | 安心して生活でき、孤独感が軽減される |
| 安心感・交流 | 精神的なゆとりが生まれる | 孫との交流が増え、心の充実や生きがいになる |
子世帯
子世帯にとって近居は、育児や親の介護といったライフイベントに柔軟に対応できる強力なサポート体制となります。以下で具体的なメリットを紹介します。
育児や教育のサポートを受けやすい


共働き家庭が増えるなかで、育児と仕事の両立は大きな課題です。急な保育園へのお迎えや、子どもの体調不良で仕事を休む必要が生じる場面は少なくありません。
このような時、近くに親が住んでいれば、すぐに駆けつけて助けてもらえます。親に子どもの面倒を見てもらえることで、共働き夫婦は育児の負担を軽減でき、仕事との両立がしやすくなるでしょう。また、教育の面でも子どもにとって祖父母の存在は大きく、学びや情緒の発達にも良い影響を与えることが期待できます。
介護が必要になったときも対応しやすい


親世帯の年齢が上がるにつれて、いつか介護が必要になる可能性は高まります。遠方に住んでいる場合、急な状況変化に対応しきれず、精神的な負担だけでなく、交通費や滞在費などの経済的な負担も大きくなりがちです。
しかし、近くに住んでいれば、親の体調が悪化した場合や、将来的に介護が必要になった際にも、すぐに駆けつけて対応できます。近居によって、親世帯は安心して老後を過ごせ、子世帯も精神的・経済的な負担を軽減しながら、無理のない介護体制を整えやすくなるでしょう。
定期的に親の健康状態を確認できる


近居は、親の健康状態を定期的に確認できることもメリットです。物理的に近い距離に住んでいれば、定期的に顔を合わせたり、一緒に食事をしたりする機会が増えます。その中で、親の体調や生活の変化に早く気づくことができるでしょう。
例えば食欲の低下、歩行の不安定さ、忘れっぽくなったなど、些細な変化でも早期に察知できれば、病気の早期発見や重症化の予防につながる可能性が高まります。また、病院への付き添いや、薬の管理、日用品の買い物といった日常的なことも、無理なくサポートできます。
親世帯
親世帯にとっても、近居は生活の質を向上させ、安心感をもたらす多くのメリットがあります。
心配事をすぐに相談できる


高齢になると、ちょっとした体調の変化や、日常での困りごとが増えてきます。そんなとき、近くに住む子世帯にすぐ相談できる環境であれば安心です。
物理的な距離が近いことで、電球交換や家具の移動など、ちょっとしたことでも相談しやすくなります。些細なことでも話せる家族が近くにいることは、不安や孤独感の軽減につながり、精神的にも安定した暮らしにつながるでしょう。
孫や子どもと関わりやすい


孫の成長を間近で見守れることは、多くの祖父母にとって大きな喜びです。近居であれば、孫と気軽に交流できる機会が増え、心の充実感や生きがいにつながります。孫との交流は認知症の予防も期待でき、健康寿命を延ばす要因にもなります。
さらに、祖父母と孫が一緒に過ごす時間が増えることで、家族の絆が深まり、世代間のつながりにも良い影響を与えるでしょう。節分や冬至といった伝統行事を孫と楽しむことで、文化の継承にも繋がります。
安心感が得られ孤独を感じにくい


高齢になると、社会的なつながりが減って孤独を感じやすくなります。しかし、近居であれば子世帯との接点が日常的に持てるため、孤立を防げるでしょう。
また、常に一緒にいるわけではなくても、近くに家族がいるというだけで、心理的な安心感が得られます。いざという時に助けてもらえる環境であることで、精神的に安定した生活を送りやすくなるでしょう。
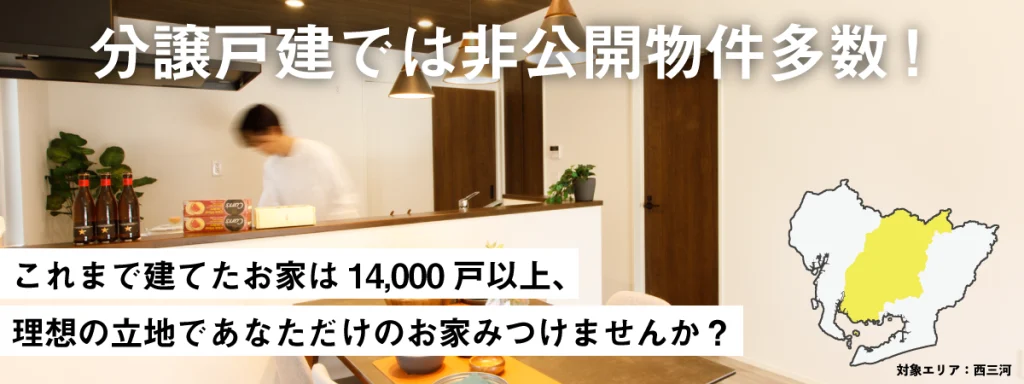
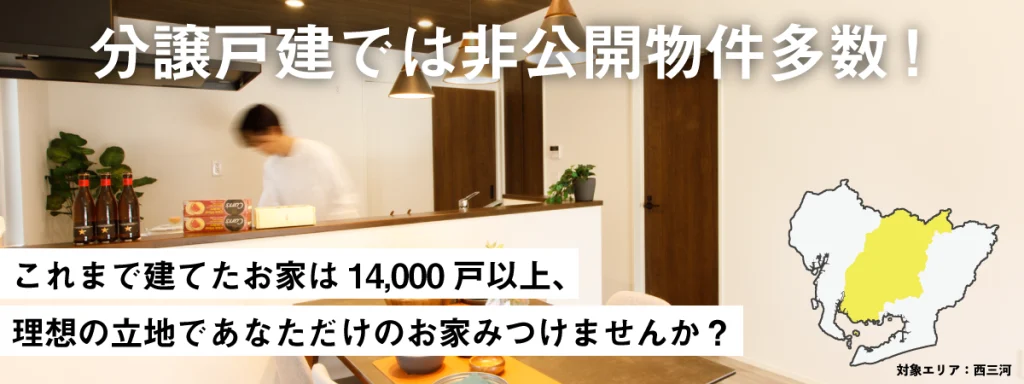
\ご希望の立地、安心のアフターサポートまで/
近居のデメリット
近居には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが、後悔のない近居生活を送るうえで非常に重要です。
近居の主なデメリットを、子世帯と親世帯それぞれの視点からまとめました。
| デメリット | 子世帯 | 親世帯 |
|---|---|---|
| 干渉・距離感 | ・親から干渉される可能性がある ・距離の取り方が難しい | ・孫の世話など頼られすぎて、負担が増える ・価値観の違いによる摩擦が生じる |
子世帯
近すぎる距離感は、逆に負担やストレスにつながるケースがあります。以下で具体例を見ていきましょう。
干渉されることがある
近居は、親世帯からのサポートを受けやすい反面、生活に干渉されることがある点がデメリットです。例えば、親が頻繁に訪ねて来る、子育てや家事に対して口出しをされるなどの可能性があります。
親としては良かれと思っての助言や行動であっても、頻度があまりに多かったり、子世帯のやり方を否定するような内容であったりすると、大きなストレスとなりかねません。親の干渉によって、夫婦の関係に軋轢が生じることもあるため、適度な距離感を保ち、お互いのプライバシーを尊重することが重要になります。
距離感の取り方が難しい
近くに住むことで、子世帯が親世帯に頼りやすくなるのはメリットです。しかし、頼りやすさが自立しにくくなる原因になり、親世帯に過度に依存してしまう可能性も秘めています。逆に、親世帯との関わりを控え過ぎると、親世帯に寂しさや不満を抱かせてしまうかもしれません。
このように、近居では物理的な距離が近い分、心理的な距離感を適切に保つのが難しいという側面があります。頼りすぎず、かといって疎遠にもならない、良好な関係のバランスを保つための努力が必要です。
親世帯
親にとっては、物理的に近いことで役割が増えすぎることに悩む場面もあります。
頼られすぎて負担が増える
孫と過ごす時間は、かけがえのないものです。しかし、孫の世話や家事の手伝いが頻繁になると、親世帯にとって体力的・精神的な負担が増大し、デメリットに転じる可能性があります。自分の時間を確保できず、自由な行動が制限されると感じ、ストレスが蓄積してしまうこともあるでしょう。
特に、高齢の親世帯にとっては、若かった頃のように無理がきかないことも多いため、注意が必要です。良かれと思って引き受けているうちに、知らず知らずのうちにストレスが溜まり、体調を崩してしまうことさえあります。子世帯との関係を良好に保ちつつ、自分のペースを大切にするための線引きが重要です。
価値観の違いによる摩擦が生じる
子世帯との距離が近い近居生活では、生活リズムや育児方針、金銭感覚など、お互いの価値観の違いが表面化しやすくなります。別々に暮らしている時には気にならなかった些細な考え方の違いも、身近になることで目に付くようになり、摩擦の原因となるかもしれません。
例えば、孫の育て方ひとつとっても、親世帯と子世帯では考え方が異なる場合があります。「昔はこうだった」といった親世帯のアドバイスが、子世帯にとっては干渉と捉えられたり、その逆の状況が起こったりもするでしょう。近居では、お互いの価値観を尊重し、歩み寄りの姿勢を持つことが大切です。
近居生活の理想と現実
近居は「ちょうどよい距離感で助け合える理想的な暮らし」として注目されていますが、実際の生活ではイメージと異なる点もあるかもしれません。
例えば、思ったよりも訪問頻度が多くなったり、逆にお互い遠慮して関わりが少なくなったりするケースもあります。
世間では「近居=安心」というイメージが強い一方、家族ごとの生活リズムや期待値の違いによって、現実とのギャップが生じることもあるため、事前に具体的な生活をイメージしておくことが大切です。
近居の後悔を防ぐためのポイント


近居を始めてから後悔しないためには、事前の準備と心構えが大切です。以下のポイントを意識して、良好な家族関係を築きましょう。
近居の後悔を防ぐためのポイント
- 生活をイメージしてから始める
- あらかじめルールを決めておく
- お互いに感謝の気持ちを忘れない
生活をイメージしてから始める
近居で後悔しないためには、実際に近居を始める前に、具体的な生活スタイルをイメージしておくことが非常に重要です。漠然とした「近くに住む」という考えだけでは、理想と現実のギャップに直面し、後悔につながる可能性があります。
例えば、親世帯への訪問頻度やサポートの範囲はどの程度になるのか、お互いのプライバシーはどのように確保するのかなど、具体的にシミュレーションしてみましょう。お互いの生活リズムや、どのような時に助けが必要になるかなどを事前に話し合うことで、具体的な近居の姿が見えてきます。生活スタイルがイメージできることで、入居後の不満を減らし、スムーズに近居生活をスタートさせることができるでしょう。
あらかじめルールを決めておく
あらかじめ親世帯と子世帯の間で明確なルールを決めておけば、トラブルを防ぎ、良好な関係を維持しやすくなります。
訪問する際は事前に連絡を入れる、週に1度は一緒に食事するなど、具体的な取り決めをしておきましょう。お互いのプライバシーを尊重し、過度な干渉を避けるための仕組みを整えることで、不必要な摩擦を減らせます。ただし、ルールは1度決めたら終わりではなく、状況の変化に合わせて定期的に見直し、必要であれば話し合って修正していきましょう。
お互いに感謝の気持ちを忘れない
日常的な助け合いがあたり前になると、感謝の気持ちを伝え忘れがちです。しかし、近居だからこそ、当たり前になりがちな助け合いに対して、お互いに感謝の気持ちを言葉にして伝えましょう。
「ありがとう」の一言があるだけで、協力関係はより円滑になり、心の距離も縮まります。また、信頼関係が深まることで、不満や摩擦が生まれにくくなります。お互いを思いやる気持ちが、良好な近居関係を長続きさせる秘訣です。
近居する際に利用できる補助金
自治体によっては、移住促進や多世代共生支援を目的に、補助金を出しているケースがあります。
例えば東京都世田谷区では、18歳未満の子どもがいる世帯が親世帯と近居をする場合、転居にかかる初期費用の一部を補助しています。補助金額は上限30万円です。大阪府茨木市では、市外に住む親世帯または子世帯が、近居のために市内へ転入する場合、住宅購入費用を補助しています。
ただし、条件や補助金額、期間などは自治体によって異なるため、まずは市区町村の窓口や公式ウェブサイトで確認しましょう。
近居と同居はどっちがおすすめ?


近居と同居、どちらが向いているかは家族構成や価値観によって異なります。同居は生活が密接になりやすいですが、近居は距離感を保ちながらサポートできる環境です。以下に両者のメリット・デメリットを表にまとめました。
| メリット | デメリット | 向いている家庭 | |
|---|---|---|---|
| 近居 | ・支援とプライバシーのバランスが取れる ・子育てや介護に対応しやすい | ・距離感の調整が難しい ・干渉される可能性 | 仕事と育児・介護を両立したい家庭 |
| 同居 | ・生活費や家賃の共有で経済的に安心 ・いつでも相談できる | ・プライバシーが確保しにくい ・価値観の違いが出やすい | 経済的な不安が大きい世帯や介護負担が重い家庭 |
近居の特徴を理解して自分たちに合ったライフスタイルを実現しよう
近居は、親世帯と子世帯が適度な距離を保ちつつ、必要に応じて助け合える暮らし方です。育児や介護の負担を軽減しながら、心の支えとなる安心感が得られます。
一方で、距離感の調整や価値観の違いには注意が必要です。後で後悔しないためにも、生活を具体的にイメージしたり、ルールを設定したり、感謝の言葉を忘れないようにしましょう。
愛知県で戸建住宅・マンション総建戸数13,000戸以上の実績を持つフジケンでは、多世代が暮らしやすい住まいづくりの相談も承っています。キッズスペース付きの『フジケンハウジングサロン』は無料で利用できるので、どうぞお気軽にご相談ください。
\分譲戸建てはこちら/
\分譲マンションはこちら/
\分譲戸建てはこちら/
\分譲マンションはこちら/