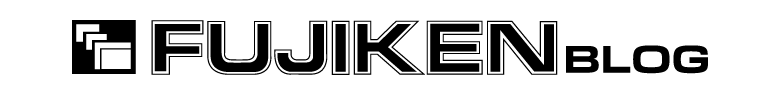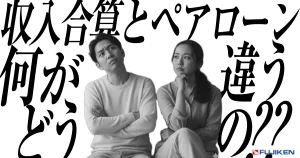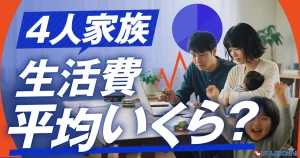マイホームの購入後には、住宅ローンの返済だけではなく、さまざまな維持費がかかります。特に、毎年必ずかかる固定資産税は、長期的な家計に大きな影響を与える可能性があるため、住宅購入を考えるうえで重要な要素です。
本記事では、一戸建ての固定資産税の平均額から計算方法、さらには具体的なシミュレーションまでを詳しく解説します。最後まで読むことで、一戸建ての固定資産税に関する疑問を解消し、安心してマイホーム購入の計画を進められるようになるでしょう。
一戸建ての固定資産税は平均いくら?

固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人に対して毎年課される地方税です。一戸建ての場合、土地と建物の両方に課税されるため、納税額はある程度まとまった金額になります。
固定資産税の標準的な税率は1.4%です。たとえば物件価格が2,000万〜4,000万円の住宅であれば、年間の固定資産税はおおよそ10万〜15万円程度が目安です。ただし、正確な金額は物件の評価額や軽減措置の有無などによって変動します。


固定資産税は変動する可能性がある
固定資産税は毎年一定ではなく、税額の基になる固定資産税評価額の見直しによって、変動する可能性があります。固定資産税評価額は原則3年ごとに見直され、土地の価格変動や建物の経年劣化などが反映されます。
そのため、築年数が経過するごとに建物の評価額が下がり、税額も減少する傾向です。一方で、地価が上昇した場合は土地の評価額が上がるため、税額が増えることもあります。固定資産税は毎年通知されるため、内容をきちんと確認しましょう。
主な変動要因
- 土地の価格変動
- 建物の経年劣化
一戸建ての固定資産税の計算方法
一戸建ての固定資産税は、土地と建物に分けて計算し、それぞれの税額を合算して求めます。以下では、土地と建物、都市計画税それぞれの計算方法について詳しく見ていきましょう。
土地の固定資産税の計算方法
土地にかかる固定資産税は「課税標準額 × 税率(原則1.4%)」という計算式で求められます。この課税標準額の基準となるのが、固定資産税評価額です。
評価額は自治体が定めた基準によって決まり、公示地価の約70%を目安に設定されます。たとえば、土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合、2,000万円 × 1.4% = 年間28万円が税額となります。
土地の固定資産税 = 土地の固定資産税評価額 × 0.014
ただし、小規模住宅用地の特例が適用されると、土地の固定資産税は大幅に軽減される可能性があります。小規模住宅用地の特例については、軽減措置の項目で詳しく説明します。
建物の固定資産税の計算方法
建物の固定資産税も、土地と同様に「課税標準額 × 税率(原則1.4%)」という計算式で算出されます。課税標準額は、新築時の建築費を基準として算出された評価額から、建物の経過年数に応じた減価償却を反映して決定されます。
一般的には、築年数が経過するにつれて建物の評価額は下がり、それに伴い固定資産税額も減少していく傾向です。新築時の評価額は、建築価格のおおよそ60%程度が目安となります。
建物の固定資産税 = 建物の固定資産税評価額 × 0.014
建物の固定資産税も、土地と同様に「課税標準額 × 税率(原則1.4%)」で算出されます。課税標準額は、建築時の建築費や建物の構造、設備なども加味したうえで設定します。資産価値が高い建物ほど、固定資産税も高くなることを覚えておきましょう。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、市街化区域内にある土地や建物に対して課される地方税です。固定資産税とは別に徴収され、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に充てられます。
都市計画税の計算式は「課税標準額 × 税率(上限0.3%)」です。ただし、税率は自治体ごとに異なり、多くの場合0.2〜0.3%の範囲内で設定されています。
都市計画税 = 課税標準(土地および建物の合計) × 0.003以下(上限0.3%)
課税標準額は固定資産税と同様に、自治体が評価した評価額をもとに算出されます。一戸建てを購入する際は、市街化区域に該当するか、そして都市計画税が課税される場合は税率も確認しておきましょう。
都市計画税の課税対象外となる地域
- 市街化調整区域(開発を抑制する区域)
- 都市計画区域外の地域(都市計画制度の対象外)
一戸建ての固定資産税に適用される軽減措置
固定資産税には、一戸建て住宅の購入者や新築住宅に対する軽減措置が設けられています。土地と建物で内容が異なるため、それぞれの軽減措置について詳しく解説します。
土地の軽減措置
住宅用地に対して、固定資産税の課税標準額が軽減される特例があります。具体的には、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準額が1/6に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は1/3に軽減されます。軽減措置の適用期限は、2026年3月31日までです。
なお、軽減措置はあくまで居住を目的とした土地に適用されるため、賃貸用や事業用の土地では対象外となることがあります。軽減措置を受けるためには、自治体へ申請が必要となる地域もあるので、担当部署に確認しておきましょう。
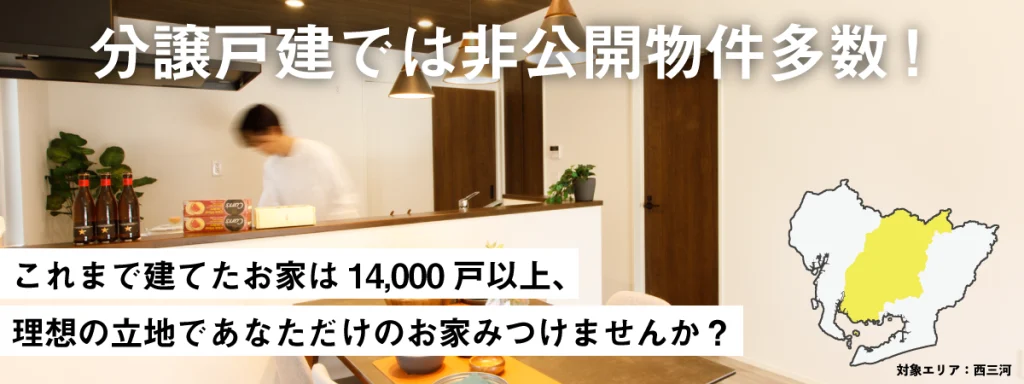
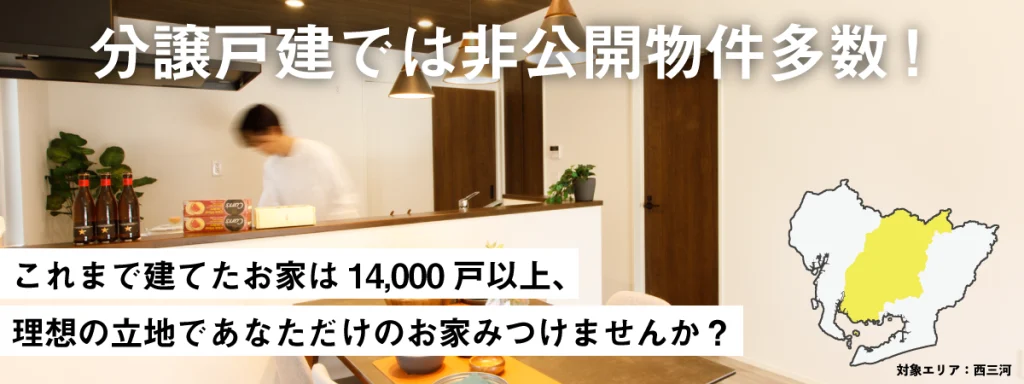
\ご希望の立地、安心のアフターサポートまで/
建物の軽減措置
新築の住宅には、固定資産税の軽減措置が適用されます。原則として新築から3年間、耐火構造の3階建て以上の建物は5年間、固定資産税が1/2に軽減されます。軽減措置の適用期限は、土地と同様に2026年3月31日までです。
軽減措置の対象となるのは、延べ床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅です。併用住宅の場合は、居住部分の面積が建物全体の2分の1以上であることが条件となります。
建物の軽減措置は、基本的には自治体が自動的に適用するため申請は不要です。しかし、特例措置の適用に関して事前申告が必要なケースもあるため、詳細は自治体に確認しておきましょう。


\岡崎、豊田、安城にモデルハウスあります!/
一戸建て固定資産税のシミュレーション
ここでは、実際に一戸建てを購入した場合の固定資産税額を、物件価格に応じてシミュレーションします。条件は以下のとおりです。
シミュレーション条件
- 土地評価額:建物価格の70%
- 建物評価額:建築価格の60%
- 税率:固定資産税1.4%、都市計画税0.3%
- 建物:新築3年以内で1/2軽減措置適用
- 土地:200㎡以下として1/6軽減措置適用
| 物件価格 | 建物の価格 | 土地評価額(70%) | 建物評価額(60%) | 土地税額(1/6軽減) | 建物税額(1/2軽減) | 都市計画税(土地+建物) | 年間合計税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 1,500万円 | 1,050万円 | 900万円 | 約2.45万円 | 約6.3万円 | 約5.85万円 | 約14.6万円 |
| 4,000万円 | 2,000万円 | 1,400万円 | 1,200万円 | 約3.26万円 | 約8.4万円 | 約7.8万円 | 約19.5万円 |
| 5,000万円 | 2,500万円 | 1,750万円 | 1,500万円 | 約4.08万円 | 約10.5万円 | 約9.75万円 | 約24.3万円 |
| 6,000万円 | 3,000万円 | 2,100万円 | 1,800万円 | 約4.90万円 | 約12.6万円 | 約11.7万円 | 約29.2万円 |
| 7,000万円 | 3,500万円 | 2,450万円 | 2,100万円 | 約5.72万円 | 約14.7万円 | 約13.65万円 | 約34.1万円 |
| 8,000万円 | 4,000万円 | 2,800万円 | 2,400万円 | 約6.53万円 | 約16.8万円 | 約15.6万円 | 約38.9万円 |
固定資産税は、以下の計算式で算出しました。
計算例
- 土地税額:土地評価額 × 1.4% × 1/6
- 建物税額:建物評価額 × 1.4% ×1/2
- 都市計画税:評価額合計(土地+建物)× 0.3%
上記の固定資産税額は、あくまで概算のシミュレーションです。固定資産税額はは、実際の評価額や軽減措置の適用状況によって異なります。
固定資産税の納付時期・支払い方法
固定資産税は年1回、指定された時期に納付します。支払いスケジュールや方法について詳しく見ていきましょう。
納付時期
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。納税通知書は4月ごろに自治体から送付され、記載された金額と納付期限に従って支払います。
多くの自治体では、納付方法として一括払いまたは、年4回の分割払い(6月・9月・12月・翌年2月)から選択可能です。支払いを忘れると延滞金が発生することがあるため、納税通知書の内容を確認し、スケジュールを事前に把握しておきましょう。
支払い方法
固定資産税の支払い方法は多様化しており、自身のライフスタイルや都合に合わせて選択できます。主な支払い方法は以下のとおりです。
| 支払い方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 金融機関窓口 | 銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関の窓口で現金または口座振替で支払う | 確実に支払えるので安心 |
| コンビニエンスストア | 納税通知書にバーコードが印字されていれば、全国の主要なコンビニエンスストアで支払う | 24時間いつでも支払いが可能、手続きが簡単 |
| 郵便局窓口 | 全国の郵便局の窓口で現金または口座振替で支払う | 全国どこでも支払い可能 |
| 自治体窓口 | 各自治体の税務担当窓口で現金で支払う | 直接相談しながら支払いができる |
| 口座振替 | 事前に登録した金融機関の口座から自動的に引き落とされる | 納め忘れがなく、手間がかからない |
| クレジットカード | 専用のウェブサイトやアプリからクレジットカード情報を入力して支払う | ポイントが貯まる場合がある、自宅で手軽に支払い可能 |
| スマホ決済 | PayPay、LINE Payなどのスマホ決済アプリを利用して支払う | キャッシュレスで手軽に支払い可能、ポイントが付与される場合がある |
| インターネットバンキング | 金融機関のインターネットバンキングサービスを利用してオンラインで支払う | 自宅にいながら支払い可能 |
近年では、クレジットカード払いやスマホ決済といったオンラインでの納付も普及し、ますます便利になっています。それぞれの特徴やメリットを考慮し、ご自身にとって最適な方法を選択しましょう。
一戸建てとマンションの固定資産税は何が違う?
一戸建てとマンションでは、固定資産税の計算方法や税額にいくつかの違いが見られます。マンションの場合、建物全体の土地を各戸の専有面積の割合に応じて共有しているため、一戸あたりの土地の固定資産税評価額は比較的抑えられる傾向です。しかし、マンションは鉄筋コンクリート造などの高強度な構造で建てられていることが多く、建物の評価額が高くなる場合があります。
一戸建ての場合は、土地の評価額がマンションに比べて大きくなる傾向があります。木造で建てられることが多く、建物の価値が比較的早く下がるため、建物に対する税負担は早期に軽減されるでしょう。
新築時の軽減措置期間は、一般的にマンションの方が長いです。しかし、固定資産税と都市計画税の総額で比較すると、長期的に見て一戸建ての方が税額を抑えやすい場合もあります。


一戸建ての固定資産税に関してよくある質問
固定資産税に関する疑問や不安は、購入前に解消しておきたいところです。ここでは、特によくある質問に対して簡潔にお答えします。
固定資産税額が上下するのはどうして?
固定資産税額が変動する主な理由は、評価額の見直しが定期的に行われるためです。評価額は、下記のような原因で変動します。
| 固定資産税額が下がる原因 | 固定資産税額が上がる原因 |
|---|---|
| ・土地の価格が下落した場合 ・建物の経年劣化(減価償却)が進んだ場合 ・税制改正により税率や軽減措置が変更された場合 | ・土地の価格が上昇した場合 ・新たな公共施設が整備され利便性が向上した場合 ・周辺の開発などにより土地の評価が見直された場合 ・建物の増築や改築によって評価額が上がった場合 |
固定資産税が高すぎるときはどうしたらいい?
税額が高いと感じた場合は、まずは評価額が妥当かを確認しましょう。評価額に疑問がある場合は、自治体に対して「評価額の見直し申請」を行うことが可能です。
それでも納得できない場合は、審査の申し出や不服申し立てといった手続きも検討できます。また、軽減措置や減免制度が利用できる可能性もあるため、自治体に相談してみることをおすすめします。