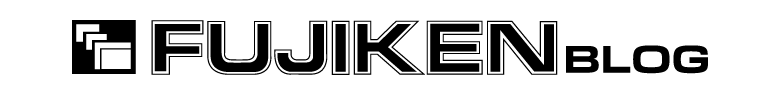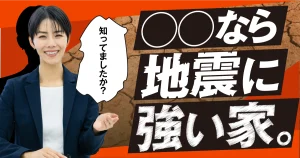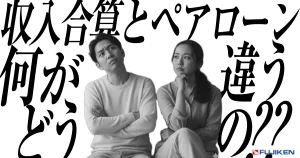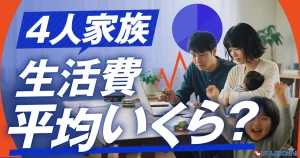マイホームの購入する際には、間取りやデザイン、住宅設備にこだわる一方で、地震や火災といった災害に備えることも重要になります。火事が起きないように注意していても、隣家からのもらい火など、自分では防ぎきれないリスクも伴うからです。
そこで知っておきたいのが、省令準耐火構造という建物の仕様です。省令準耐火構造は火災に強く、万が一の際も大切な家族や家を守るための重要な要素となります。この記事では、省令準耐火構造の詳しい特徴やメリット・デメリット、さらに火災保険料との関係まで、わかりやすく解説します。
省令準耐火構造とは?わかりやすく解説


わかりやすく簡潔に説明すると、省令準耐火構造とは、住宅金融支援機構が独自に定める基準を満たす構造です。建築基準法で定められたものではなく、財務省と国土交通省所轄の省令として設定されています。省令準耐火構造の基準を満たした建物は、火災に強いと認定され、さまざまな優遇措置を受けられます。
省令準耐火構造の家は、万が一の火災が発生した際にも、火の燃え広がりを遅らせ、避難や消火活動のための時間を稼ぐことが可能です。火災が発生した場合、初期消火や避難行動が非常に重要になります。省令準耐火構造なら、延焼を遅らせることで、焦らずに対応できる時間を与えてくれます。
また、保険会社に火災リスクの低い建物と判断され、火災保険料の割引も適用される点もメリットです。火災保険料の割引は、長期的な住宅コストの削減につながります。
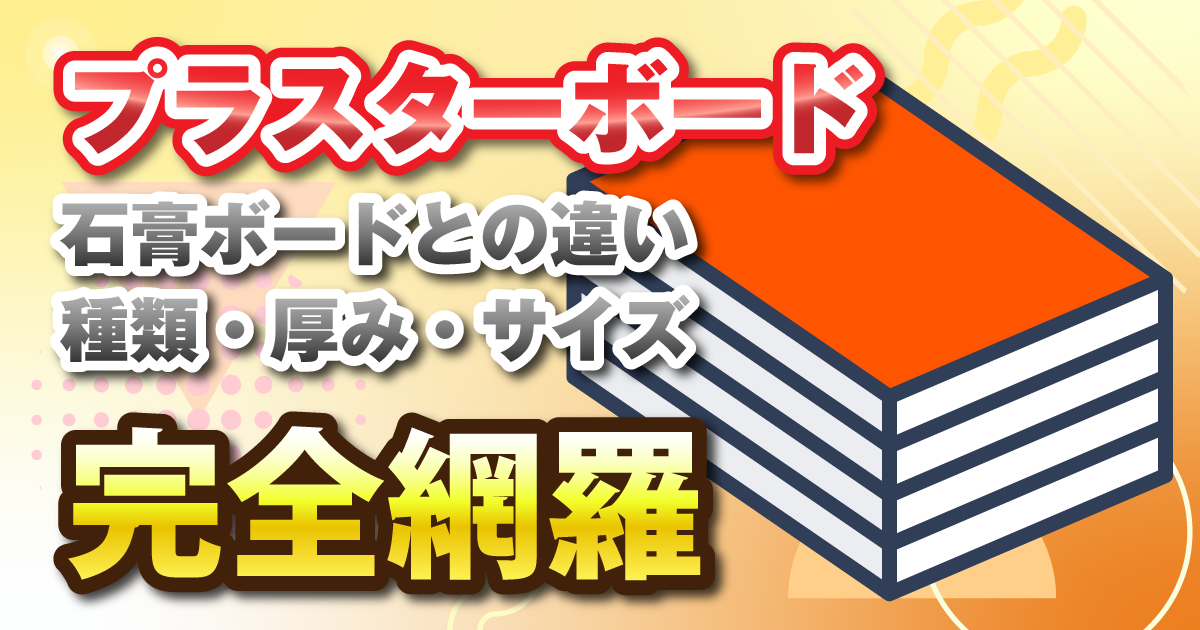
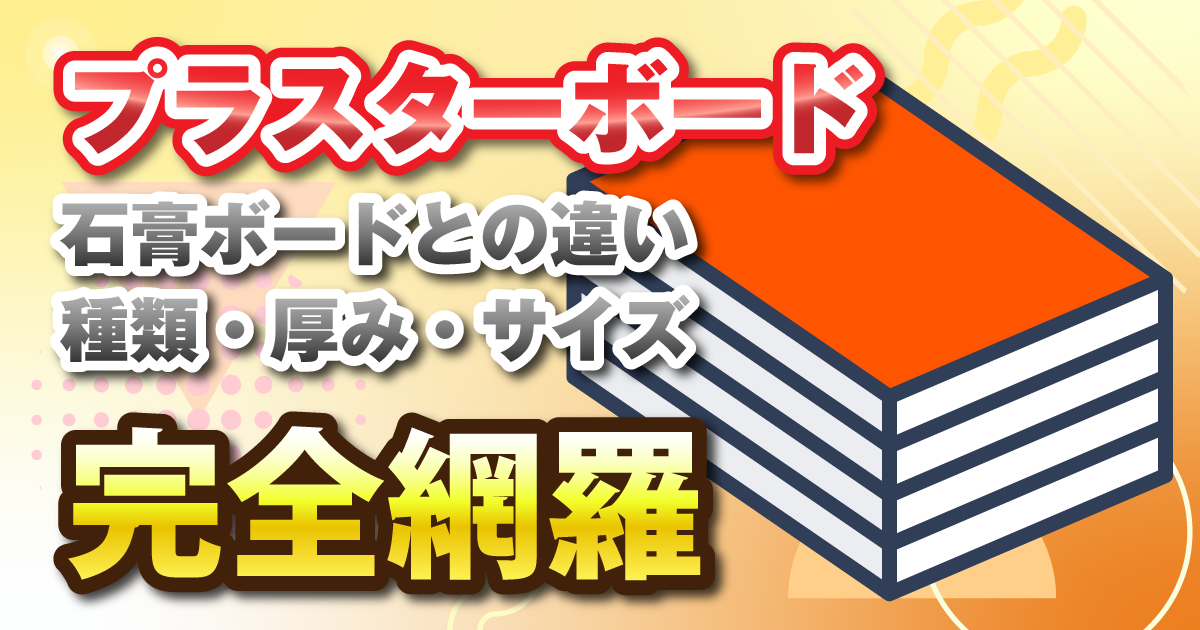
耐火構造・準耐火構造との違い
耐火構造と準耐火構造は、建築基準法で定められた耐火性能を持つ建物です。これらの構造は、都市部の防火地域や準防火地域に建築される際に義務付けられています。火災時の倒壊や延焼を防ぐために厳しい基準が課せられており、柱や梁、壁などの建物の主要構造部が、火災の熱に一定時間耐えられる設計です。さらに、コンクリートや鉄骨に耐火被覆を施すなどの措置がとられます。
一方、省令準耐火構造は、住宅金融支援機構の基準に基づく仕様です。建築基準法上の義務ではなく、建物の安全性を高めるための任意の仕様として位置付けられています。
性能基準を満たせば省令準耐火構造として認定され、準耐火構造と同等レベルの性能とみなされます。法律で耐火構造が義務付けられていないエリアでも、自主的に省令準耐火構造を採用することで、高い防火性能を備えた住宅を建てることが可能です。
省令準耐火構造の特徴


省令準耐火構造には、以下の3つの大きな特徴があります。
省令準耐火構造の特徴
- 隣家からのもらい火を防ぎやすい
- 火災が起きても一定期間は火が広がらない
- 火が広がっても延焼を遅らせる
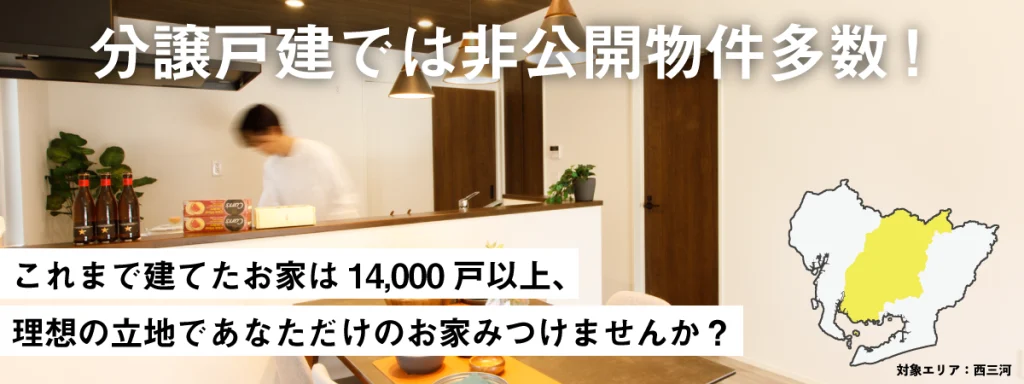
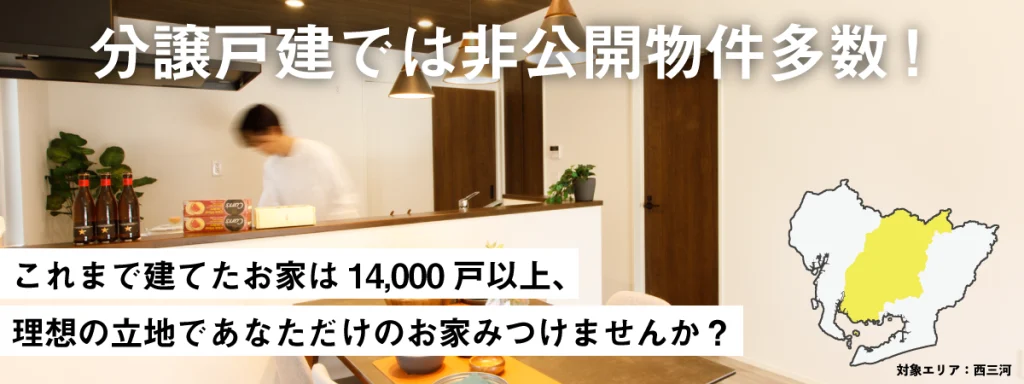
\ご希望の立地、安心のアフターサポートまで/


\岡崎、豊田、安城にモデルハウスあります!/
隣家からのもらい火を防ぎやすい
省令準耐火構造は、外壁や屋根に不燃材や耐火性能の高い建材を使用していることが特徴です。特に、屋根の軒裏や外壁の構造が強化されており、燃えやすい軒下部分から火災の熱や火の粉が建物内部に侵入するのを防ぎます。
そのため、隣家での火災によって火の粉が飛んできても、屋根材や外壁が燃え広がりづらく、被害を最小限に抑えられます。住宅が密集した地域でも、もらい火のリスクを軽減できるため安心です。
火災が起きても一定期間は火が広がらない
省令準耐火構造は天井や壁、床などに耐火石膏ボードや不燃材を使用しています。耐火石膏ボードとは、耐火性能を強化した不燃材料です。そのため、室内で火災が発生しても、一定期間は火が燃え広がりません。
炎が別の部屋に到達するまでの時間を延ばすことで、居住者が安全に避難するための時間を確保できます。また、火の進行を一時的に食い止めることで、被害範囲を最小限に抑えられるでしょう。
火が広がっても延焼を遅らせる
省令準耐火構造は、内部の構造材や下地に耐火処理が施されています。対価処理には、万が一、建物全体に火が広がり始めたときにも、延焼を遅らせる効果があります。
木造住宅についても、鉄骨や耐火被覆を組み合わせることで、火災時の倒壊や延焼リスクを低減することが可能です。これにより、消防活動の時間を確保し、全焼を防ぐ可能性が高まります。また、火事のリスクを前提に設計されているため、長期的に安心して暮らせる住宅となるでしょう。
省令準耐火構造のメリット
住宅を省令準耐火構造にすることには、以下のようなメリットがあります。
省令準耐火構造のメリット
- 火災時の被害を最小限に抑えられる
- 火災保険料を抑えられる
- 地震保険料を抑えられる
火災時の被害を最小限に抑えられる
省令準耐火構造は、火災の被害を最小限に抑えられることが最大のメリットです。前述のとおり、建物内部で火災が発生しても燃え広がりにくく、隣家からのもらい火を防ぐ効果もあります。
居住者の安全な避難時間を確保できるだけでなく、家財への損害を抑えることも可能です。特に、小さな子どもやお年寄りがいるご家庭では、避難時間を確保できることは大きな安心材料となります。また、住宅の損傷が少なければ、再建費用や生活再建の負担も軽減されるでしょう。
火災保険料を抑えられる
火災保険料は、建物の構造によって変動し、構造が火災に強いほど保険料を抑えられます。火災保険の契約において、住居用の建物構造は「M構造(マンション構造)」「T構造(耐火構造・準耐火構造)」「H構造(非耐火構造)」に分けられます。
省令準耐火構造はT構造に位置付けられ、H構造に分類される一般的な木造住宅よりも、保険料が安価です。保険料の差は、年間数万円に及ぶこともあり、長期的に見ると数十万円、場合によっては100万円以上のコスト削減につながることもあります。
地震保険料を抑えられる
地震保険も火災保険と同様、構造によって保険料が変動します。地震保険では、建物の構造が「イ構造(鉄骨造、コンクリート造)」と「ロ構造(木造)」に分けられます。
イ構造は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐震性能が高い構造です。ただし、木造であっても省令準耐火構造に認定されていれば、イ構造に分類されます。ロ構造に比べて、イ構造の建物は地震保険料が安価です。省令準耐火構造にすることで、より低い保険料で地震に備え、家計の負担を軽減できます。
省令準耐火構造のデメリット
省令準耐火構造には、以下のようなデメリットも存在します。
省令準耐火構造のデメリット
- 建築コストが高くなりやすい
- 間取りやデザインの自由度が下がる
- 維持およびメンテナンスコストも高くなる可能性がある
建築コストが高くなりやすい
省令準耐火構造にするためには、使用する素材や工法を火災に強い仕様に変更する必要があります。そのため、建築コストが高くなりやすい傾向です。一般的な木造住宅と比較して、数十万円から100万円程度の追加費用が発生するケースもあります。
もちろん、火災リスクを下げられるという点は大きなメリットです。しかし、予算を設備のグレードアップや間取りの工夫に充てたい場合には、コスト増はデメリットと感じるかもしれません。
間取りやデザインの自由度が下がる
省令準耐火構造では、不燃材や耐火建材を使うため、デザインの選択肢が制限されることがあります。また、窓やドアのサイズにも制限があり、間取りにも制約が生じる可能性が高いです。基本的に、柱や梁を露出することはできず、開放的なデザインにするのも難しいでしょう。
そのため、自由度が下がる点を考慮したうえで、火災に強い家を建てるかよく吟味することが大切です。耐火性能とデザイン性の両立を目指すならば、専門家とよく相談しましょう。
維持・メンテナンスコストも高くなる可能性がある
耐火性の高い素材は、建築時だけでなく、メンテナンス時にもコストが高くなる可能性があります。たとえば、外壁の塗り替えや屋根の補修を行う際、一般的な建材ではなく、特殊な材料や専門的な技術が必要になる場合があるからです。
建築コストと同様に、メンテナンスにかかるコストについても、長期的な住宅計画に含めて検討しましょう。
省令準耐火構造に関してよくある質問


省令準耐火構造について、よくある質問をまとめました。
省令準耐火構造かどうかの確認方法はありますか?
省令準耐火構造かどうかの確認方法は、2つあります。
1つめは、建物の設計仕様書や設計図面で、省令準耐火構造であるか自身で確認する方法です。これらの書類は、建物を新築した際に、ハウスメーカーや工務店から受け取ります。
特に、仕様書に記載されている「省令準耐火構造の仕様」や「防火性能に関する記載」を確認しましょう。建築確認申請書には、省令準耐火構造であることまでは記載されないので、確認の際は注意が必要です。
2つめは、ハウスメーカーに問い合わせる方法です。書類を見てもわからない、あるいは紛失したという場合は、ハウスメーカーに確認してみましょう。
省令準耐火構造の証明書はもらえますか?
省令準耐火構造の証明書は発行していません。代わりに、建物の仕様が省令準耐火構造の基準を満たしていることを示す「木造住宅等である旨の証明書」や「建物検査結果報告書」が発行されます。
これらの書類は、火災保険や地震保険の契約時に保険会社へ提出することで、保険料の割引を受ける際に必要となります。適合証明書には、省令準耐火構造であることまでは記載されないので注意しましょう。
省令準耐火構造はいつから始まったのですか?
省令準耐火構造はいつから始まり、すでに建築した自宅でも認定されるのか、気になる方もいるでしょう。省令準耐火構造は、2023年4月1日に改正されました。そのため、2023年4月1日以降に物件検査を申請する建物から、現在の仕様が適用されます。
なお、2023年以前に建築された建物でも、過去の基準を満たしていれば省令準耐火構造と認められる場合があります。詳細については、建築したハウスメーカーや工務店に確認するといいでしょう。
省令準耐火構造の特徴を押さえて住宅設備を考えよう
省令準耐火構造は、火災に強い家を実現するための重要な要素です。隣家からのもらい火を防いだり、火災が起きても延焼を遅らせたりする効果があり、火災時の被害を最小限に抑えられます。また、火災保険料や地震保険料を抑えられるという経済的なメリットも魅力です。
一方で、建築コストや維持費が高くなること、間取りやデザインの自由度が制限されるといったデメリットもあります。理想の住まいを建てるためには、これらの特徴を理解したうえで、予算やライフスタイルとのバランスを考慮することが大切です。
火災に強い家づくりについて、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にフジケンまでお問い合わせください。フジケンの分譲住宅は、耐火性が高い「強化プラスターボード」を採用しており、省令準耐火建物に認定されています。住宅性能の詳細については、公式サイトでご確認いただけます。