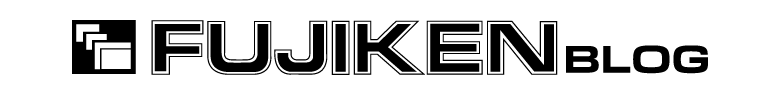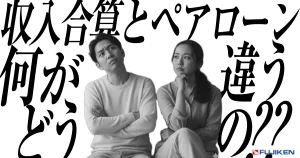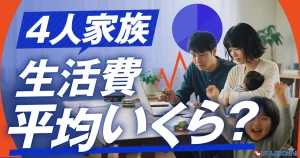住宅を購入するならば、誰しも「できるだけ長く快適に暮らしたい」と考えるでしょう。そこで知っておきたいのが、国が推進する『長期優良住宅』です。長期優良住宅は、高い耐震性や省エネ性、将来のメンテナンス性などに優れた住宅を対象に、さまざまな税制優遇や住宅ローンの優遇措置が受けられます。
この記事では、長期優良住宅の定義や認定基準、メリット・デメリット、認定を受けるまでの流れについて分かりやすく解説します。ことで、あなたの家づくりの選択肢が広がり、より賢く理想のマイホームを手に入れるヒントが見つかるはずです。
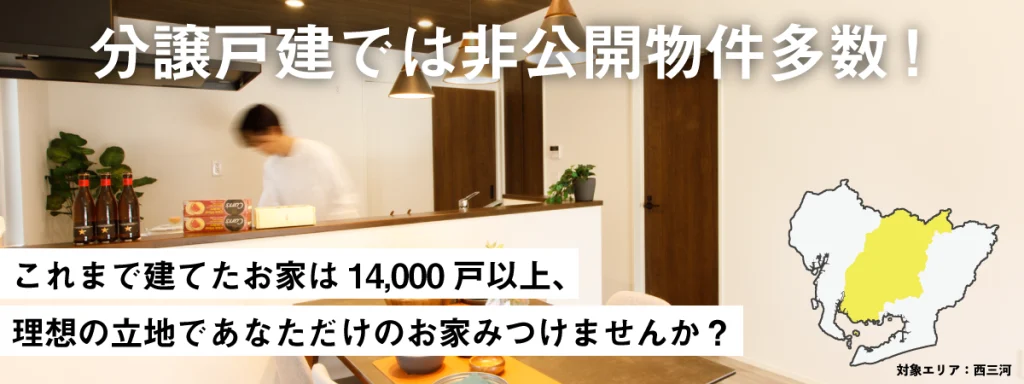
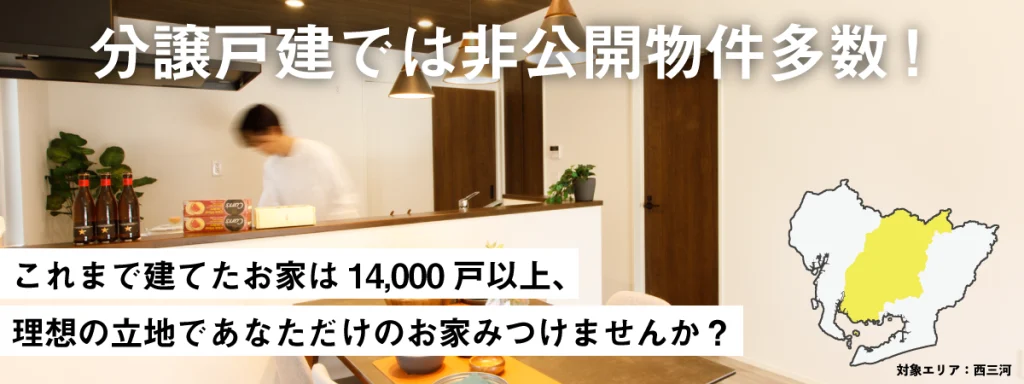
\ご希望の立地、安心のアフターサポートまで/
長期優良住宅とは?


長期優良住宅とは、国が定めた認定基準を満たし、長期間にわたって安心して住み続けられる高性能な住宅のことです。具体的には、耐震性や省エネ性、劣化対策など、住宅性能に関する厳格な基準をクリアした住宅が対象となります。また、住む人のライフスタイルの変化に対応できる柔軟性や、メンテナンスのしやすさなども考慮されています。長期優良住宅として認定されると、税制優遇や住宅ローンの金利優遇措置など、さまざまなメリットを受けられることも大きな魅力です。
長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅として認定されるためには、国が定める複数の厳しい基準をクリアする必要があります。ここでは、新築時の認定基準について詳しく見ていきましょう。
| 認定項目 | 概要 |
|---|---|
| 劣化対策 | 構造部材の劣化を抑える措置が講じられていること |
| 耐震性 | 地震による損傷を軽減し、改修が容易な構造であること |
| 省エネルギー性 | 必要な断熱性能等が確保されていること |
| 維持管理・更新の容易性 | 内装・設備の点検・修繕を容易に行える措置が講じられていること |
| 可変性 | 家族構成の変化に対応できる構造であること(共同住宅等) |
| バリアフリー性 | 高齢者・障がい者の暮らしやすさに配慮された設計であること(共同住宅等) |
| 居住環境 | 周辺のまちづくりや景観と調和していること |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保できる広さがあること |
| 維持保全計画 | 定期的な点検・補修の計画が立てられていること |
| 災害配慮 | 自然災害リスクに対応した安全性が確保されていること |
劣化対策


長期優良住宅では、住宅の構造躯体が長期間の使用に耐えられるよう、劣化対策等級3以上の性能が求められます。構造部材が数世代にわたって維持されるような措置が講じられていることが基準です。加えて、構造の種類に応じた基準を満たす必要があります。
| 構造の種類 | 劣化対策の主な概要 |
|---|---|
| 木造 | 床下空間の高さの確保、床下・小屋裏への点検口設置 |
| 鉄骨造 | 構造体の錆を防ぐための防錆対策 |
| 鉄筋コンクリート造 | 水セメント比の減量、かぶり厚さ(鉄筋を覆うコンクリートの厚さ)の増幅 |
耐震性


地震大国である日本において、耐震性は長期優良住宅の重要な認定基準のひとつです。極めてまれに発生する規模の大地震後でも、簡単な修繕で引き続き居住できるレベルの強度が求められます。具体的には、以下のいずれかを満たしている必要があります。
| 耐震性の認定要件 | ・耐震等級2以上であること ・耐震等級1の基準に適合し、安全限界時の層間変形を1/100(木造は1/40)以下とすること ・耐震等級1の基準に適合し、かつ各階の張り間方向・けた行方向が所定の基準に適合するもの(鉄筋コンクリート造等に限る)であること ・免震建築物であること |
|---|
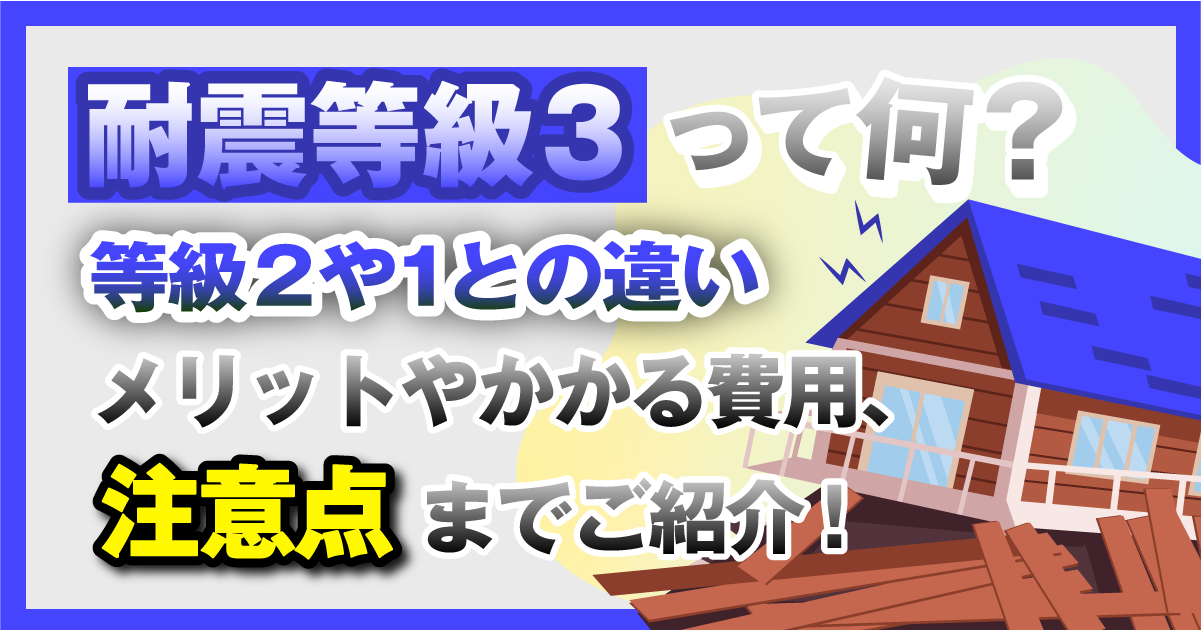
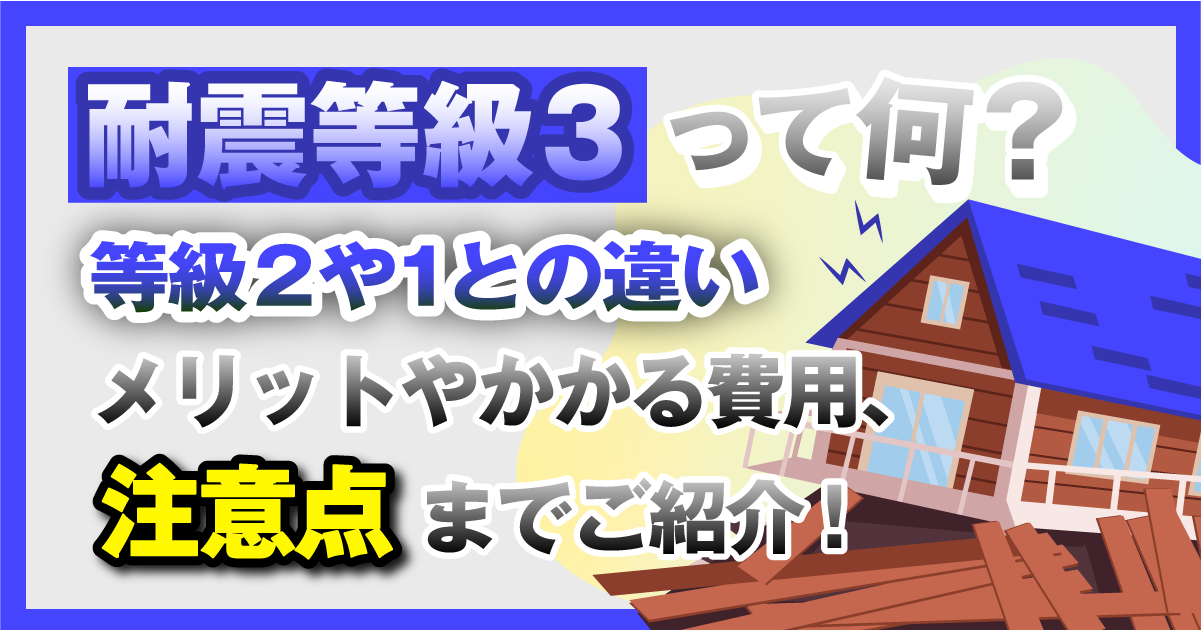
省エネルギー性


長期優良住宅は、高い断熱性とエネルギー効率を備えていることも求められます。これにより、冷暖房のエネルギー消費を抑え、光熱費の削減と地球環境への配慮を両立できます。
基準としては、断熱等性能等級5以上、または一次エネルギー消費量等級6以上の性能が必要です。高効率な給湯器や断熱材の使用が該当します。
維持管理・更新の容易性


住宅の長寿命化には、将来的な点検や修繕の容易性も不可欠です。長期優良住宅では、給排水管や配線などの設備について、床下や天井裏から容易にアクセスできる構造であることが求められます。維持管理・更新の面で容易性が長期優良住宅に適合していれば、将来的な修繕費用や手間を抑えられるでしょう。
| 戸建て | 戸建て 維持管理対策等級(専用配管)等級3であること |
|---|---|
| 共同住宅 | ・維持管理対策等級(共用配管)等級3であること ・更新対策(共用排水管)等級3であること |
可変性


可変性の項目では、家族構成の変化やライフスタイルの変化に合わせて、間取りを変更しやすい構造であることが求められます。具体的には、天井高が2,650mm以上であることが基準です。
将来的に間仕切り壁を撤去したり、新しい間仕切りを設置したりしやすい設計とすることで、長く快適に暮らし続けられます。
バリアフリー性


バリアフリー性とは、高齢者や障がいのある人でも安心して暮らすために必要な基準です。住宅への出入りや移動がスムーズにできるよう、段差を極力なくし、廊下や出入口の幅を広く取るなどの設計が求められます。共同住宅等では、共用部分において、高齢者等配慮対策等級3の基準を満たす必要があります。
居住環境


長期優良住宅では、住宅そのものの性能だけでなく、周囲のまちづくりや景観との調和も重要視されます。地方公共団体の都市計画や条例などと整合性が取れていることが、認定の条件です。
例えば、生活環境の維持に貢献する立地・設計であったり、良好な景観であったりすることが求められます。そのため、地域によっては、住居の高さやデザインなどが制限される場合があります。
| 居住環境の認定要件 | ・地区計画、景観計画、条例等の区域内にあっては、その内容と調和していること ・市町村の定める「良好な景観の形成に関する指針」や「まちづくりの誘導に関する指針」などと整合していること ・接道要件を満たしていること |
|---|
住戸面積


長期にわたって快適に暮らすためには、一定以上の広さも必要です。長期優良住宅では、原則として住戸の床面積が75㎡以上であることが求められます。また、集合建住宅の場合は、一戸あたりの床面積が40㎡以上であることが基準です。
ただし、地域の実情に応じて、所管行政庁が基準を別途、定めている場合もあります。
| 住戸の種類 | 必要な面積 |
|---|---|
| 戸建て | 75㎡以上(少なくとも1つの階の面積が40㎡以上であること) |
| 共同住宅 | 40㎡以上 |
維持保全計画


維持保全計画では、点検・補修の計画を立て、長期にわたって住宅の性能を維持することが求められます。具体的には、点検や補修の周期・内容などを記載した維持保全計画を作成します。なお、構造躯体や防水、給排水設備などの主要部位について、定期的な点検・修繕の実施時期が明示されていなければなりません。
| 定期的な点検時期・適切な補修の計画を策定する部分 | ・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水または排水設備 |
|---|
災害配慮


災害配慮とは、水害や土砂災害などの自然災害へのリスクを考慮した立地や設計であることです。長期優良住宅では、水害・土砂災害などのリスクが高い区域において、安全性を確保するための十分な対策が講じられていることが条件となります。
ただし、災害に配慮した設計でも、長期優良住宅として認められないエリアもあるので注意しましょう。
| 災害配慮の認定要件 | ・災害発生リスクが高い区域では、災害に配慮した構造や対策が講じられていること ・地すべり防止区域、急傾斜崩落危険区域、土砂災害特別警戒区域に該当しないこと |
|---|
長期優良住宅の認定を受けるメリット
長期優良住宅の認定を受けることで、以下の優遇措置を受けられます。
長期優良住宅の認定を受けるメリット
- 住宅ローンの金利を引き下げられる
- 税の特例措置を受けられる
- 地震保険料の割引が適用される
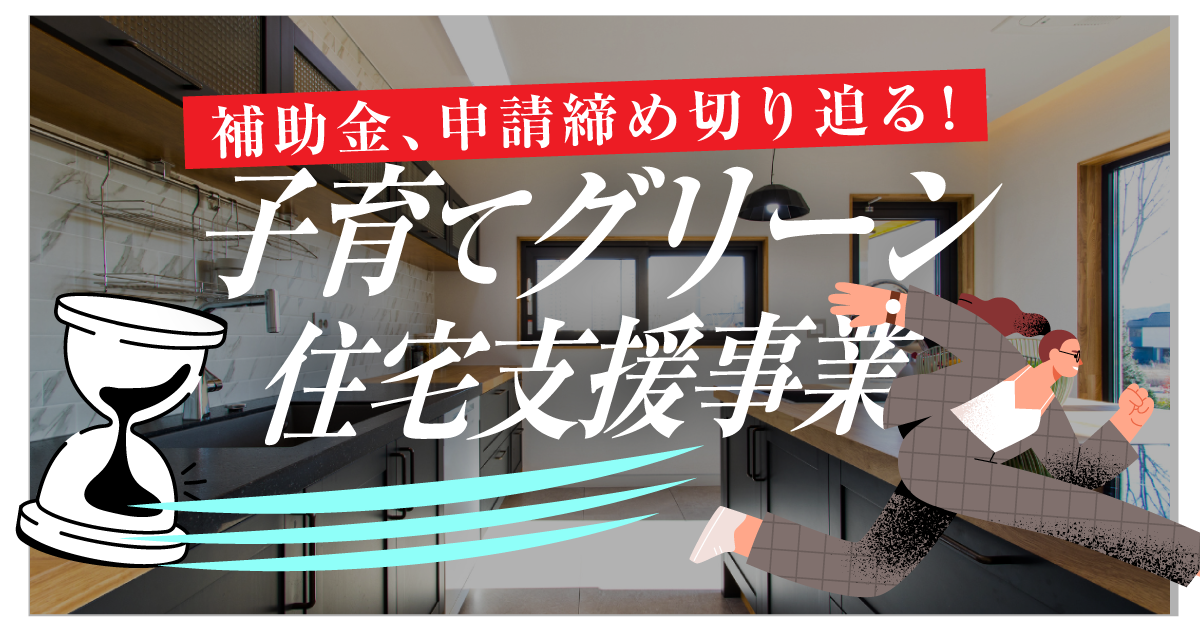
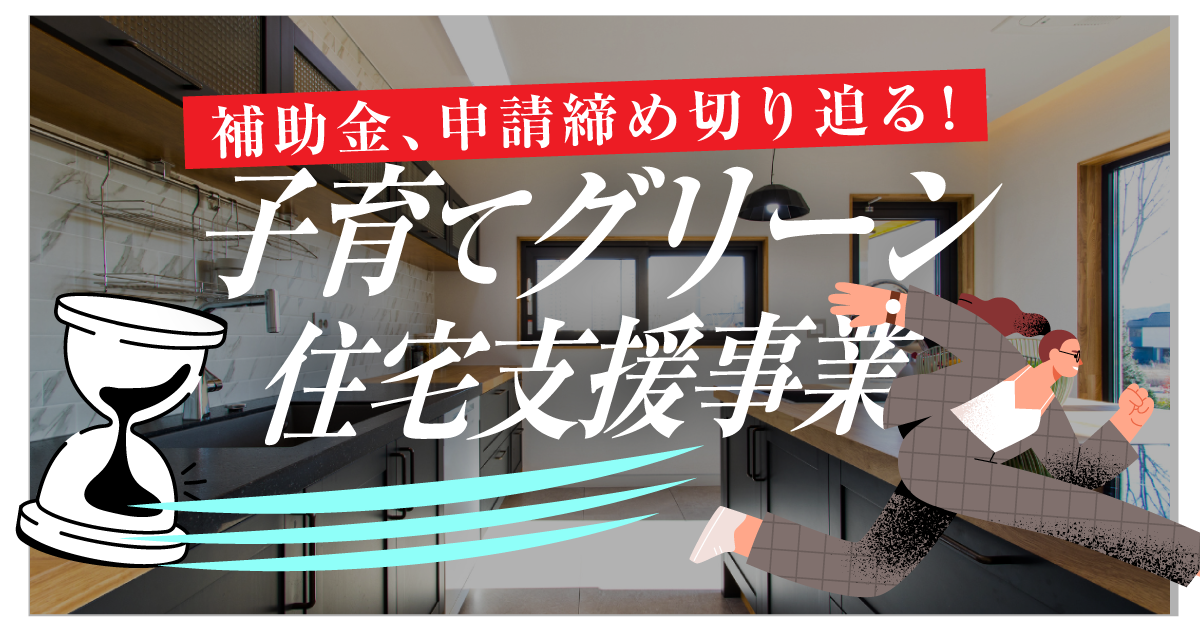
住宅ローンの金利を引き下げられる
長期優良住宅の認定を受けると、住宅ローンの金利引き下げが期待できます。例えば、フラット35では、長期優良住宅に認定された場合、当初の金利を一定期間引き下げる『フラット35 S』の利用が可能です。
フラット35 Sの金利Aプランでは、当初5年間は年075%の金利引き下げが適用され、家計にゆとりを持たせられます。また、フラット50では返済期間を最長50年間に設定できるので、家計にゆとりを持たせることが可能です。
高性能な住宅を建てるには一定の初期コストがかかりますが、金利優遇によって長期的には経済的メリットを得られます。民間金融機関の住宅ローンでも、長期優良住宅向けの優遇金利を設定している場合があるので、各金融機関に確認してみるといいでしょう。
税の特例措置を受けられる
長期優良住宅は、税制面でも多くの特例措置を受けられます。例えば、住宅ローン控除の控除対象限度額が、一般住宅よりも高く設定されており、所得税を軽減できることがメリットです。
また、登録免許税の税率が引き下げられたり、不動産取得税や固定資産税の軽減措置が適用されたりするなど、入居後の税負担が抑えられる仕組みも整っています。
| 住宅ローン控除(所得税の優遇)・住宅ローン残高の0.7%を最長13年間控除 | ・控除の対象となる借入れ限度額を4,500万円まで引き上げ ・子育て世帯と若者夫婦世帯は借入れ限度額を5,000万円まで引き上げ ※2025年12月31日までに入居の場合 |
| 不動産取得税の控除額拡充 | 住宅を取得した際に課される不動産取得税が、1,200万円から1,300万円に増額 ※2026年3月31日までに新築された住宅 |
| 固定資産税の減額期間延長 | ・戸建て住宅は最長3年間から5年間に延長 ・マンションは最長5年間から7年間に延長 |
| 登録免許税の税率引き下げ | ・保存登記の登録免許税が0.15%から0.1%に引き下げ ・移転登記(戸建て)の登録免許税が0.3%から0.2%に引き下げ ・移転登記(マンション)の登録免許税は0.3%から0.1%に引き下げ ※2027年3月31日までに新築された住宅 |
地震保険料の割引が適用される
長期優良住宅は、一定の耐震性が保証されていることから、地震保険料の割引制度の対象になります。例えば、耐震等級2以上の住宅であれば、地震保険料が30%割引されます。さらに、耐震等級3であれば50%割引と、経済的な負担を大幅に軽減できる点がメリットです。
地震保険料は、住宅の構造や面積、立地によっては年間5万円ほどかかるケースもあり、長期的に見ると高額な支払いになります。そのため、住宅を購入する際は、地震保険料の割引が適用されるかも大きな判断材料になります。


\岡崎、豊田、安城にモデルハウスあります!/
長期優良住宅の認定を受けるデメリット
多くのメリットがある一方で、長期優良住宅の認定を受けることにはデメリットも存在します。
長期優良住宅の認定を受けるデメリット
- 時間やお金がかかる
- 一般的な住宅よりも建築コストが高くなる可能性がある
- 入居後も定期的なメンテナンスや点検が必要になる
時間やお金がかかる
長期優良住宅の認定を受けるためには、設計段階からの計画や書類作成、所管行政庁への申請など、通常の住宅建築よりも手続きが煩雑になります。また、申請にかかる費用のほか、性能評価機関による審査に伴うコストも必要です。
結果として、初期費用も割高になる可能性があるため、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。さらに、設計事務所や建築会社との打ち合わせ回数も増える傾向にあり、施主の時間的負担も少なくありません。手続きの流れを把握したうえで、設計事務所や建築会社と連携し、スムーズな認定取得を目指しましょう。
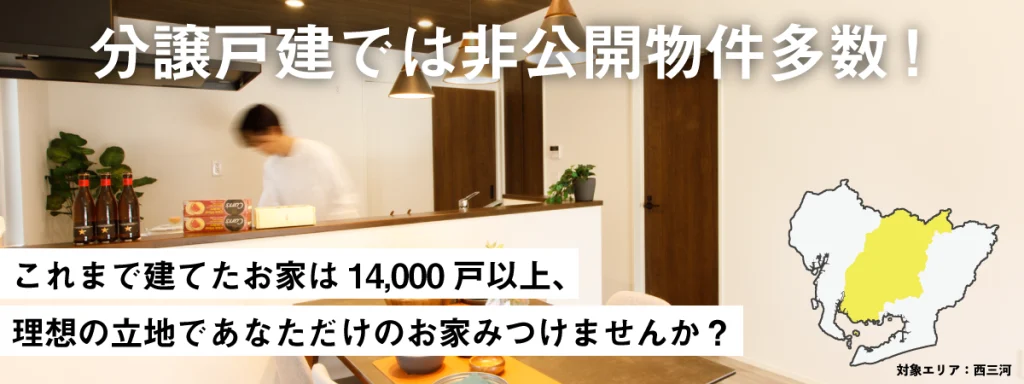
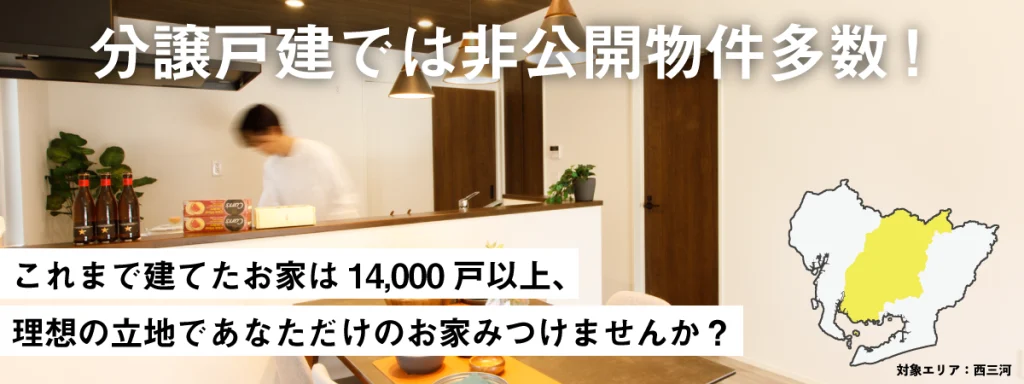
\ご希望の立地、安心のアフターサポートまで/
一般的な住宅よりも建築コストが高くなる可能性がある
長期優良住宅の認定を受けるためには、断熱性や耐震性、劣化対策など、国が定めた複数の基準を満たす必要があります。これらの基準をクリアするには、高性能な建材や構造部材の導入が求められるため、一般的な住宅よりも建築コストが高くなる傾向です。
もちろん、住宅ローンの金利引き下げや税の特例措置といった優遇もあります。しかし、初期費用としては割高になる点を踏まえ、ライフプランに応じた慎重な判断が必要です。また、省エネ設備や長寿命の建材は、長期的にはランニングコスト削減や修繕費の抑制につながるケースもあります。そのため、短期的なコストだけでなく、トータルでの費用対効果を見極めたうえで検討することが重要です。
入居後も定期的なメンテナンスや点検が必要になる
長期優良住宅では、維持保全計画の策定が義務付けられており、認定を維持するためには定期的な点検や補修が必要です。たとえば、10年ごとを目安に、外壁や屋根、配管などの状態を確認し、必要に応じて修繕を行います。
こうした保守管理には、費用や手間がかかるものの、建物の性能を長く保つためには欠かせない取り組みです。また、定期的なメンテナンスを計画的に実施することで、資産価値を維持できるので、将来的に売却することになったときも値段が下がりづらいでしょう。
長期優良住宅の認定手続きの流れ
長期優良住宅の認定を受けるためには、定められた手続きを踏む必要があります。ここでは、一般的な流れを解説します。
事前相談・設計
建築会社や設計事務所に相談し、長期優良住宅の認定基準を満たす設計を進める。
必要な書類
- 建築プラン
- 配置図
- 立面図 など…
技術的審査の申請
建築基準法に基づく建築確認申請と並行して、長期優良住宅の技術的審査機関に申請し、適合していると判断されれば確認書が交付される。
必要な書類
- 認定申請書
- 設計図書
- 造計算書 など…
所管行政庁への申請
所管行政庁に認定申請を行い、認定基準を満たしていると判断されれば認定通知書が交付される。
必要な書類
- 確認書
- 認定申請書 など…
工事の完了報告
工事が完了したら、所管行政庁に完了報告書を提出する。
必要な書類
- 完了報告書
- 工事写真 など…
入居後の維持保全
認定を受けた後は、維持保全計画に基づき、定期的な点検や補修を実施し、記録を保管する
必要な書類
- 点検記録
- 修繕記録 など…
長期優良住宅の特徴を踏まえて認定を受けるか判断しよう
長期優良住宅は、耐震性や省エネ性、劣化対策などに優れ、将来にわたって安心・快適に暮らせる住宅です。認定を受けることで住宅ローンや税制の優遇、地震保険料の割引といったさまざまなメリットが得られます。
一方で、申請手続きや建築コスト、維持管理の負担があることはデメリットです。自分や家族のライフスタイル、将来的な住まいのあり方を見据えたうえで、長期優良住宅の認定を受けるかどうかを検討しましょう。
フジケンでは、長期優良住宅の設計・申請に関するご相談も承っています。創業50年長のノウハウを活かし、一人ひとりに合わせたアドバイスをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。